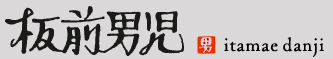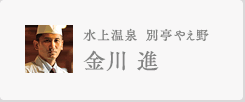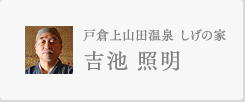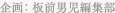長野県千曲市を流れる千曲川の左岸。明治中期に開湯し、善光寺参りの精進落としの湯として賑わった戸倉上山田温泉。そして昭和30年代の後期、散髪に出向く父に連れられ、大勢の観光客で賑わう温泉街を歩く少年の姿があった。大勢の観光客に向けた遊技場や飲食店、店先のガラス棚に並ぶ模型など、街中は少年にとって飽きることの無い遊び場でもあった。家の周辺は野山に包まれ、「桑の実」や「あけび」をおやつに友人たちと駆け回る。冬は、掘りごたつの灰に入れて焼いた「ニンニク」のホクホクとした味が忘れられないと言った。
中学を出た吉池は、名古屋では珍しかった叔父の営む山菜料理店にて1年働く。その後、「将来のためにちゃんとした所で修行した方が良い」と叔母のすすめで高山にある大きな日本料理店へと移ることになる。店の特色は、「飛騨の小京都」と呼ばれる城「高山」の郷土料理。初代は地元の名店で修行を積み、生粋の高山料理とともに一代で自分の店を大きくした。そして京都の有名料亭で修行を重ねた二代目は店に京懐石の感性と技術を持ち帰った。様々でいながら正統的な日本料理を出すこの店で、本格的な修行を始めたことが自分の料理の基盤となったと吉池は語る。

朝は自転車で朝市に仕入れに出かけ、仕事終わりに鰹節を削るのが吉池の日課だ。一つ年上の先輩を良き競争相手とし、いつも負けないように頑張った。料理は「見て覚える」が当たり前で、「やってみろ」と言われたときには確実にこなせるよう常に心がけた。料理の修行は厳しかったが、世は高度成長期の最中であり楽しい時代だったと振り返る。

そうして5年が過ぎた頃、吉池は本店に隣接する出店を任される。高級懐石が主たる本店に対して、一般の人に日本料理を親しんでもらうための昼食が中心である。吉池は厨房内で本店の料理を手伝う一方で、出店では客前での調理を両立させた。カウンター越しで作る料理はごまかしがきかない。その分食べた瞬間の表情で「美味しかったかどうか」が読み取れた。このことが一番の経験だと吉池は言う。
高山のこの店で13年間を過ごした吉池は、子供が生まれることをきっかけに故郷「戸倉」へと戻る決意をする。知人に紹介された新しい職場は、温泉街で一番大きな団体旅館。毎日大勢の宿泊客が訪れる中、調理場では1日に300から500食もの夕食が、流れ作業で作られて行く。午後の二時から揚げ始める天ぷらなどは、夕食時には当然すっかり冷めてしまう。「これは料理ではない」長らく料理屋で働いてきた吉池にとっては、全てが戸惑いの連続となった。「旅館には行くなよ」高山の店を辞める時の二代目の一言が頭をよぎっていた。煮方として調理場の二番手になり、4年目に差し掛かろうとした頃、吉池に新たな転機が訪れる。
![]()
![]()
戸倉上山田温泉に「しげの家」という一風変わった宿があった。
元々は主(あるじ)自らが包丁を振るっていた宿だ。料理人として本格的な修行こそしていないが、客を喜ばせるための創意工夫を凝らしていた。例えば、今では珍しくない朝食に出す「茶碗蒸し」も、当時は贅沢な「もてなし」として話題になった。主に変わり調理場に入った初代料理長は長く勤めあげたが、二代目の時にトラブルが起こる。正月を迎えるための忙しい年末の仕込みを前に急にスタッフが足りなくなったのだ。騒然となる宿を後に、主は料理人を探すべく奔走した。そこで聞きつけたのが、同じ温泉地で料理人としての将来を考えあぐねていた吉池の噂だった。悩む吉池に早く来いとせっつく主、ここから料理長として30年近いキャリアを重ねる宿「しげの家」との出会いは、そんな慌ただしい出来事がきっかけとなる。

当時の「しげの家」は、現在の女将の父親である初代の好みとバブル期の勢いが重なった「金ピカ」な指向だった。客層も男性を中心とした接待客が多く、料理も酒に合わせた「豪華」な食材が売りだった。周辺の宿が軒並み鉄筋コンクリートの近代旅館として大型化する中、図面まで出来ていた「宴会場と客室を増やして4階建てにする」女将の計画を「そこまでする気はない」と中止させた。以来「しげの家」は、絢爛と洗練が調和した設えとともに、木造八室の小体な佇まいのままである。「俺は宿で客を呼ぶから、お前は料理で呼んでみろ」。自分に料理を託してくれた初代の言葉が、今も忘れられないと吉池は言う。
![]()
 |

高山の日本料理店にて修行を重ね、1985年より故郷戸倉上山田温泉の宿「しげの家」料理長に就任 |